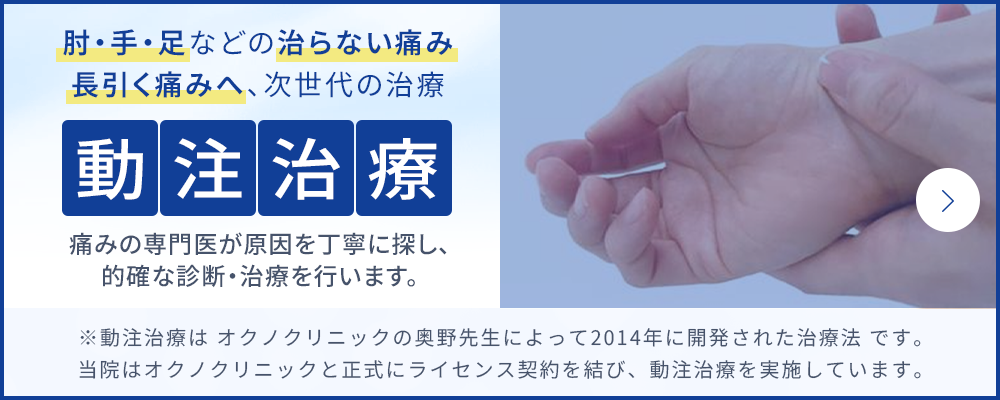- HOME>
- 頭の痛み
頭の痛み
頭の痛みは痛む場所に個人差があり片側だけ、両側、さらには痛みが移動するように感じる場合もあります。吐き気を伴う場合も珍しくありません。さまざまな原因で頭痛が生じ対処法が大きく異なりますが、CTやMRIなどの検査をしても原因が特定できない場合もあります。原因が明らかでない頭痛は一次性頭痛と呼ばれ、片側頭痛や緊張性頭痛が代表的です。ペインクリニックでは主にこれらを治療します。
一方で二次性頭痛はくも膜下出血、脳出血、脳腫瘍など脳の異常に原因がある病気が代表的ですが、生命が脅かされる場合や緊急治療を要する場合が少なくありません。頭痛にお悩みの患者様で何科を受診すればよいか困っている方はぜひ当院にご相談ください。
片頭痛

片頭痛とはズキズキとした拍動性の痛みが頭の片側に出る病気です。ただし両側に出る場合や非拍動性の痛みもあります。吐き気・嘔吐などの症状を伴う場合や、いつもなら気にならない音・光・臭いが我慢できないほど不快に感じる場合、さらには歩くだけでも痛みが強くなるためにじっと寝ているしか対処法がない場合も少なくありません。個人差はありますが頭痛は数時間から3日程度持続します。
未だに詳しい原因やメカニズムは明らかになっていません。日本では成人の約8.4%が片頭痛を患っていると報告されており、女性に多い特徴があります。従来の薬では治し方が難しい病気でしたが近年新しい注射薬が使用可能となり、症状軽減に大きな成果を挙げています。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は頭痛の中でも多いタイプの1つで、頭を締め付けられる、あるいは圧迫されるようなにぶい痛みが多いなど、「ズキズキ」した拍動性の痛みではありません。多くの場合は頭の両側が痛み、持続時間はさまざまです。吐き気を伴う場合も少なくありません。
長時間のパソコン作業やスマートフォン操作など負担のかかる姿勢による頭・首・肩の筋肉の緊張が原因と考えられています。また精神的ストレスの関与も少なくありません。治し方には筋緊張を和らげる体操・ストレッチや痛み止めを中心とした薬などがあります。ただし痛み止めの乱用でかえって頭痛が治らない場合があるのでご注意ください。なおコーヒーの緊張型頭痛に対する善悪は確立されていません。
脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が減少するために頭痛、耳鳴り、めまいなど多彩な症状が起こる病気ですが、自然治癒する場合があるのか、そもそも治る病気なのか、など詳細は不明です。脳脊髄液量を直接測定する方法がないために診断基準は確立されておらず、難病指定はありません。
脳脊髄液減少症の存在自体を疑問視する専門家もいます。一方で脳脊髄液の圧力や脳脊髄腋が外に漏れ出すかは検査可能なので低髄液圧症候群や脳脊髄液漏出症の病名が使用される場合も少なくありません。交通事故による鞭打ち・転倒・打撲などの外傷や全身への強い衝撃が原因で発症すると考えられており、治療法としてブラッドパッチ療法を試みる場合があります。
非定型顔面痛
非定型顔面痛では上の奥歯や顎を中心にうずく、圧迫される鈍痛を生じて不快な痛みが続いて気になる、集中できないなどの悩みが出ます。三叉神経痛(詳しくは<三叉神経痛>参照)、舌咽神経痛、後頭神経痛など他の顔面痛を生じる疾患に当てはまらない病気であるために非定型顔面痛の診断は難しく、患者様は何科を受診してよいか困る場合やいくつもの診療科(耳鼻科、内科、歯科など)・医療機関を転々とする場合が珍しくありません。
原因は明らかではありませんが漢方薬が有効な場合があります。他の頭痛治療でよく使用する消炎鎮痛薬の効果は乏しいので痛みを感知する脳に何らかの変化を生じているのではないかと考えられています。